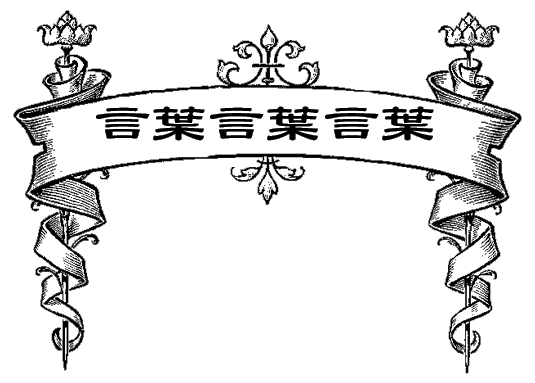
|
|
|
言葉 言葉 言葉! |
| 哲学 てつがく
〈哲学〉という言葉は,明治初年の段階で, 西周 (にしあまね)によって,英語の〈フィロソフィーphilosophy〉の訳語として作られた。 〈フィロソフィー〉は,ギリシア語の〈フィロソフィアphilosophia〉に由来し, 〈知恵 (ソフィアsophia) を愛する (フィレイン philein) 〉という意味の言葉である。そこで西周は,周濂渓 (れんけい)の〈士希賢 (士は賢をこいねがう) 〉 (《通書》志学) にならい,賢哲の明智を愛し希求するとの意で,はじめ〈希哲学〉 (哲智すなわち明らかな智を希求する学) と訳し,のちに〈哲学〉と定めた (《百一新論》1874)。西周は,草創期の明治政府の知的指導者の有力な一人であったから,この〈哲学〉という訳語はやがて文部省の採用するところとなり,以来日本で一般に用いられることになった。
【ギリシアにおける哲学】
〈知を愛する (フィロソフェイン philosophein) 〉とは,古代ギリシアにおいて,はじめ,世間ならびに人生についての知恵を愛し求めるという意であった。それは,この言葉の文献上の初出とされるヘロドトスの《歴史》 (1 巻 30 節) が伝えるギリシアの賢者ソロン (前 7 世紀後半〜前 6 世紀前半) の場合である。ソロンは,多くの国々を“知を愛し求めつつ”旅行し視察し遍歴したといわれる。ソロンにとって,人生上,世間上の知恵とは,神々を畏敬し人間の有限性をわきまえるということであった。次いで前 6 世紀後半以降,ピタゴラス学派において, 〈愛知〉は,名利を離れて知を愛求するという意に深められたようである。
これらの考えを受けて,前 5 世紀後半のソクラテス,およびその弟子プラトンの段階に至って,ギリシアにおける〈愛知〉の意味はほぼ確定した。ソクラテスおよびプラトンによれば,人間にとってたいせつなこと最も尊いことは,単に生きることではなく,むしろよく生きることである。その場合の〈よさ〉とは何であるか。これを求めることが〈フィロソフィア (愛知) 〉である。個人の栄達や富貴,また国家の強盛や栄光は,個人や国家を真に幸福にさせるものではない。それらのものは,個人の所有するものであり,国家の所有するものではあるが,決して個人そのものでも,国家そのものでもない。真実の知恵は,個人そのもの国家そのものが,真によくあることを目ざすものでなければならぬ,と。それは今日の言葉でいえば,個人や国家共同体の,精神的主体性の〈よさ〉が求められたということである。 〈よさ〉とは,あるべき姿,すなわち善美であること (カロカガティア) であるが,プラトンにおいて,善や美は,〈イデアidea〉あるいは〈エイドスeidos〉とせられた。イデアあるいはエイドスとは,ともに〈見る idein〉という動詞に由来し, 〈見られたもの〉を,したがって見られたものの〈かたち (形) 〉,あるいは〈すがた (相) 〉を意味する。それは,ものの真実の在りよう,在るべき姿を意味する。生成し消滅し流転する多様の存在からなる感性的世界を超えて,不変恒常の〈真実有 (ウシアousia =実体) 〉であるイデアが求められ,このイデアとしての善や美を仰ぎ見ながらわれわれの魂を善美にととのえ,またこの世を善く美しく調和あるものとすることが,プラトンにおける〈愛知 (哲学) 〉の究極の目標であった。 アリストテレスが求めたものもまた,真実有としての〈エイドス (形相) 〉の探究であった。 このようなギリシアの哲学は,やがて紀元後のローマ時代に,キリスト教がその教理を形成する際に有力な手がかりとなり,教理の中へ採り入れられた。このことによってキリスト教は,ユダヤ民族の一分派宗教であることを超えて,普遍的国際的な宗教となるに至った。こうしてギリシアにおける知への愛=哲学は,キリスト教の一神論によって改釈され,唯一最高の神が有する知への愛となるに至ったのである。 山崎 正一 |
|
[印欧語における〈愛〉の語彙] そこで,中国語の〈愛〉の原義と,印欧語の主要な〈愛〉を表現する名詞の素朴な意義とを,順序不同に紹介しておくことにする。 〈愛〉は,母親の幼児にいだく〈せつない愛情〉が自然な発語として定着したもので,少なくとも中古以後は,〈ai〉という二重母音が,完全に一体ではありえないが別個の存在というにはあまりにも不可分な,母子関係の緊密さを,潜在意識に感じさせていたと憶測される。 〈母性愛〉のあらわれであるから,〈与える愛・いつくしみ〉が本義である。 これに対して,ラテン語〈amor (イタリア語 amore,フランス語 amour,スペイン語 amor) 〉は,幼児が母の〈乳房〉を慕う際の発声が起源で,ラテン語〈mamma (乳房) 〉,日本語〈mamma (食物) 〉,日本語と朝鮮語の〈omo (母) 〉と同じく,もっとも発声が容易でしかも吸着行為の口の動きと密接な,両唇音を主体としている。したがって,本来は,〈求める愛〉である。 英語〈love〉,ドイツ語〈Liebe〉などは,印欧原語〈leubh〉にさかのぼることができ, 〈愛・あこがれ・親しみ〉など,広い意味をもっていた。フロイトの〈リビドー〉の原語である,ラテン語〈libido〉は,〈激しい欲望〉を本義とする,この群に属する語である。 ギリシア語〈erヾs〉は,〈性愛〉を指すのが普通であった。これに対して,ギリシア語〈philia〉は, 〈philos (形容詞=親愛なる,名詞=友人) 〉に由来し, 〈友愛・友情〉である。しかし,〈philos〉の原義は,ホメロスが用いた〈自分自身の〉であり,リュディア語〈bilis (自分自身の) 〉に代表される,アナトリア語が起源らしい。 〈自分自身の (もの) 〉だから〈いとしい〉という発想は,ほかにもあり,サンスクリット語〈priya (いとしい) 〉〈preman (愛) 〉がその例であるが, 〈priy´ (いとしいもの,形容詞・女性形) 〉に対応するものとして,北欧や古代高地ドイツ語の女神名〈Frigg〉〈Fr ̄ja〉があり,英語の〈Friday (金曜日) 〉に名残りをとどめる。また,〈自分自身の (からだ) 〉だから,奴隷でなく〈自由〉だというのが,英語,ドイツ語〈free〉〈frei〉 (自由な) の原義であり, 〈自分の (側に立つ人) 〉というのが,英語,ドイツ語〈friend〉〈Freund〉 (友人) の本義である。 ギリシア語〈agap^ (愛) 〉は,動詞〈agapaヾ (好意をもつ・愛情をもつ・好む・満足する) 〉から,比較的おそく造られた語で,〈性愛〉であることはまれだったので,新約の用語として採用された。 ラテン語〈caritas (愛・愛情) 〉は,形容詞〈carus (イタリア語・スペイン語 caro,フランス語 cher,親愛なる) 〉に由来し,ギリシア語〈agap^〉の訳語とされて,キリスト教的〈愛〉を指すようになり,さらに,〈愛〉にもとづく〈慈善〉の意をもつようになった (カリタス)。英語〈charity〉の語源でもあるこの語が,サンスクリット語〈k´ma (欲求・愛欲) 〉と同根であるらしいのは,いかに語の意味内容が移ろいやすいかということのよい見本である。 松山 俊太郎 |
|
感受性 かんじゅせい affectivity‖sensibility 外界からの感覚的,感情的な働きかけを受けいれる,人間の心の能力あるいは状態。大別して,認知的感受性と情動的感受性との二つがある。前者は,感性知覚にもとづいたもので,色彩,形,音の特性,匂いや香りについての感覚を豊かにしてくれ,この場合には感覚性とも呼ばれる。後者はより全体的なもので,快楽や苦痛の感情を受けいれる能力あるいは状態のことであり,この場合には感情性とも呼ばれる。またこの両者を含んだ感受的な心的事実の総体をさす場合には, 感性とも呼ばれる。この感覚や感情を含んだ感性は,永い間概して非哲学的あるいは反哲学的なもの,すなわち理性や思考の敵,人間を動物に近づけるものだと思われてきた。しかし現代では,無意識や身体性の問題と結びついて大きな哲学的問題となってきている。 中村 雄二郎 |
感性 かんせい 英語のsensibility,ドイツ語のSinnlichkeitなどの訳語として使われる用語。もろもろの感官による感覚的認識能力一般から,ときに感情をも総称する用語として使われる。感覚的認識能力としての感性は,通常,知性,理性,悟性等何らかの意味での知的認識能力に対立するものとして使われ,また感性の語が主として感情の意味に重きをおかれるときには,知性と意志とに対立するものとして使われるのが一般である。古代ギリシア以来,感性は,受動的なものであり,したがって確実な認識をもたらすことのないものとして,知性や理性にたいして低く位置づけられ,感情もまた,とりわけ中世の哲学においては,おなじく受動的であるゆえに,理性や善を意志の自由な発現をさまたげるものとして,低い位置をあたえられるのを常としてきた。しかし,一方で,人間の心の構成を, 直観的な感性,間接的推論による認識をこととする理性,高次の直観にかかわる知性の 3 段階で考える行き方がギリシア以来中世にわたる,とくにプラトン主義の伝統の中にあり,この知性による直観と感性的直観とが直観というかぎりで共通することから,重ね合わせられ融合されると,ときに感性にたいする高い評価が生じてくる。ルネサンス時代の美的汎神論から,スピノザの能動感情 (actio,通常の受動的感情 passio に対立) の考え,また近世イギリスの美的道徳的感情の哲学などがその代表例である。この傾向は,さらに,近代科学の登場にともなう認識論の領域での感性の役割を重視する経験論や感覚論の哲学の台頭と合流して,ドイツ,イギリスのロマン派からフランスのスピリチュアリスムに通じる感性の中に知性の根ともなる積極的能動的要素の芽を見る行き方につながっていく。現代では,さらに記号論的構造論的手法を導入して,感性の中に知的なものと同質な論理をさぐる方向が新たな色どりをそえている。 ⇒感受性 坂部 恵 |
