
![]()
![]()
![]()

![]()
![]()
![]()
 世界のミュージアム
世界のミュージアム 厳粛なる遊び、アドヴェントカレンダーの十日目。
今日は香港(中国)です。
![]() 香港
香港
20世紀21世紀の「伝統的な視覚芸術以外の視覚文化領域の幅広い工芸品を展示する」
.mplus.org.hk/about-the-collection/
![]() モダンアート、ちょっと興味がわかないですね(;'∀')でも
モダンアート、ちょっと興味がわかないですね(;'∀')でも
(面積)最大規模の美術館のリストに含まれるだけでなく、
最も訪問者数が多い美術館のリストにもあるようだ(16位) (en,wikipedia)
北京の故宮博物院の分館
一般入場は100香港ドル(1950円)(シニア50ドル )
2022年7月開館
北京の故宮博物院から借り受けた陶美術品914点のほか、フランス・パリのルーブル美術館からも作品を借りている
![]() 私がもし行くとしたらこちらメインでしょうか?(M+と同じ地区にある)
私がもし行くとしたらこちらメインでしょうか?(M+と同じ地区にある)
![]() 今、中華人民共和国(北京)へは直行便で3時間ですが、ビザが必要だと思っていたら、「2024年11月30日から2025年12月31日まで、一般旅券保持者であれば30日以内の滞在であればビザは不要。」に。
今、中華人民共和国(北京)へは直行便で3時間ですが、ビザが必要だと思っていたら、「2024年11月30日から2025年12月31日まで、一般旅券保持者であれば30日以内の滞在であればビザは不要。」に。
2024年11月22日、中国外交部は停止していた日本国籍向けの短期滞在査証免除措置について、2024年11月30日から措置を再開すると発表しました。
コロナ禍で出なかった『地球の歩き方』、ようやく刊行され始めましたね♪
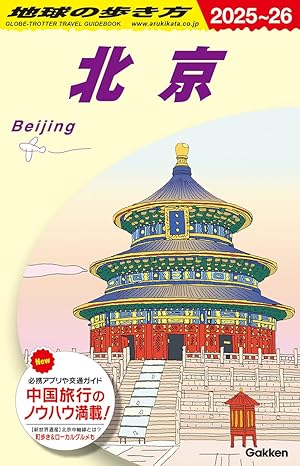
Gakken (2024/11/14)新刊

The Forbidden City - View from Coal Hill
景山からの神武門の眺め
![]() 陶磁器、山水画、花鳥画、肖像画、宗教画、書、硯、時計、彫刻・・・こちらにCollections リスト
Collections_of_the_Palace_Museum
陶磁器、山水画、花鳥画、肖像画、宗教画、書、硯、時計、彫刻・・・こちらにCollections リスト
Collections_of_the_Palace_Museum
![]() 比較して
比較して
Collections of the National Palace Museum.
![]() そういえば、京都の泉屋博古館(https://sen-oku.or.jp/)で、世界有数と名高い住友コレクションの中国青銅器を見たことがありました・・
そういえば、京都の泉屋博古館(https://sen-oku.or.jp/)で、世界有数と名高い住友コレクションの中国青銅器を見たことがありました・・
打楽器で「編鐘」というんですよね。
(wikipedia)
お土産は「虎卣」のレプリカ。(souda-kyoto.jp)
![]() このページを書くために『文房具の考古学』というのを見てみました。
このページを書くために『文房具の考古学』というのを見てみました。
文字が持つ芸術性はともかく、権威というのがなるほど・・・
この6月刊 山本 孝文著 吉川弘文館
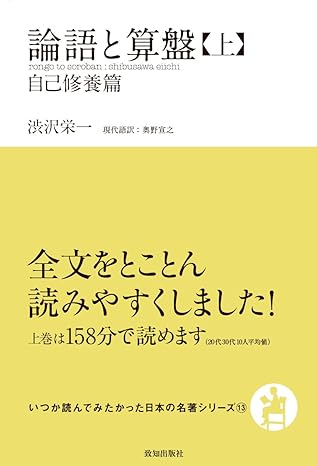
論語と算盤(上) (自己修養篇)
(下)人生活学篇
渋沢栄一 (著), 奥野宣之 (翻訳)
致知出版社 (2016/7/29)刊
![]() 今年後半の私メの一大イベントは家の中の片付け(断捨離(;^_^A)
今年後半の私メの一大イベントは家の中の片付け(断捨離(;^_^A)
そこで、たまたま出てきた、『論語』の書き抜きノートであるが、例に漏れず、「学而第一」と「為政第二」辺りで終わってました・・・・それで、今回、中国ドラマを見ながら、この際全文制覇!を目指し、続きを書きぬいていました。現「顔淵第十二」まで来ました。
新1万円札の顔となる渋沢栄一が著した、国民的ベストセラー
タイトルは
(いつか読んでみたかった日本の名著シリーズ)
『論語』は誰もが使える実用的な教訓で、論語とソロバンは一致すべきものだ、という話なのだが。
また、資本主義というのはともすれば「自分えもうかれば他人はどうでもいい」というモラル破壊になりがちであること。そうならないために「論語」のような道徳の教えで制御しなければならない、と、
 ⇒2024年12月11日 へ
⇒2024年12月11日 へ