

今年のテーマは星。惑星を見ています。昨日の木星についで、今日は土星を。
![]()
![]()
![]()

土星♄(どせい、ラテン語: Saturnus、英語: Saturn)は、太陽から6番目の、太陽系の中では木星に次いで2番目に大きな惑星である。巨大ガス惑星に属する土星の平均半径は地球の約9倍に当る。平均密度は地球の1/8に過ぎないため、巨大な体積の割りに質量は地球の95倍程度である 。そのため、木星型惑星の一種と分類されている。
土星の内部には鉄やニッケルおよびシリコンと酸素の化合物である岩石から成る中心核があり、そのまわりを金属水素が厚く覆っていると考えられ、中間層には液体の水素とヘリウムが、その外側はガスが取り巻いている。
惑星表面は、最上部にあるアンモニアの結晶に由来する白や黄色の縞が見られる。金属水素層で生じる電流が作り出す土星の固有磁場は地球磁場よりも若干弱く、木星磁場の1/12程度である。外側の大気は変化が少なく色彩の差異も無いが、長く持続する特徴が現れる事もある。風速は木星を上回る1800km/hに達するが、海王星程ではない。
土星は恒常的な環を持ち、9つが主要なリング状、3つが不定的な円弧である。これらはほとんどが氷の小片であり、岩石のデブリや宇宙塵も含まれる。知られている限り82個の衛星を持ち、うち53個には固有名詞がついている。これにはリングの中に存在する何百という小衛星(ムーンレット)は含まれない。
タイタンは土星最大で太陽系全体でも2番目に大きな衛星であり、水星よりも大きく、衛星としては太陽系でただひとつ有意な大気を纏っている。
日本語で当該太陽系第六惑星を「土星」と呼ぶ由来は、古代中国において五惑星が五行説に当てはめて考えられた際、この星に土徳が配当されたからである。英語名サターンはローマ神話の農耕神サートゥルヌスに由来する。(wikipedia 土星 閲覧20201217)
その天文学のシンボル(♄)はサートゥルヌスの鎌を表しています。
自転によって惑星は扁球形状を持ち、極よりも赤道部分が膨らんだ扁平状になっているために、極半径と赤道半径の差はほぼ10%(60,268km 対 54,364km)にもなる。

This captivating natural color view of the planet Saturn was created from images collected
shortly after Cassini began its extended Equinox Mission in July 2008.
探査機カッシーニ撮影
サトゥルスヌス
農耕が時を刈り取るという意味も持ち農耕神のクロノスが時の神として混同されて扱われる時があるようにサートゥルヌスにも同様の傾向が見られる。
農耕神とも時の神とも、または農耕と時の両方を司ると扱われている時もあり文献によって扱いが異なっている。
ただし古代から農耕の収穫などの周期は重要であり、農耕神は時を司る神として扱われていたという説もある。
彼を祀る神殿(サートゥルヌス神殿)は、ローマの七丘の一つカピトリヌスの丘のふもとのフォルム・ロマヌムの西端にあり、ここにはローマの国庫が置かれ、また法文や元老院決議が保管されるなど、政治的にもきわめて重要な神殿だった。
彼の祝祭はサートゥルナーリア(Sāturnālia)と呼ばれ、毎年12月17日から7日間執り行われた。その間は、奴隷にも特別の自由が許され、楽しく陽気に祝われた。
後世への影響
サートゥルナーリア祭では、人々はろうそくや小さな人形を贈物として交換した。この風習は、のちにキリスト教におけるクリスマスに受け継がれたという。
※一般には(
ブリタニカ百科事典では)、クリスマスは、冬至の後の太陽の復活を祝う古代ローマの習慣に日付を合わせたとしている(ミトラ教)。

アゴスティーノ・ディ・ドゥッチョ(Agostino di Duccio)1418‐81 kotobankモデナ大聖堂の祭壇浮彫を制作(1442)リミニでテンピオ・マラテスティアーノの装飾に従事(1449ころ‐57ころ)

15世紀イタリアの獣帯と星神に関するつづきもの一部。
子どもを食べる時の神としての土星を表わす。
アレゴリー的表現が重要であって、文字通りに取る必要はない。
(『占星術 天と地のドラマ』p114)
・・ということだが、この主題の絵画、おぞましい。
ゴヤが自分の食堂を飾るために作った6つの作品(黒い絵1819-1823)の1つなど。(「崇高な恐ろしい」のスタイル)
ギリシア神話では、クロノスは生まれたばかりの子を「飲み込む」のであるが、ルーベンスのもゴヤのも、成長している人間を食べている。
[我が子を食らうサトゥルヌス Saturn Devouring His_Son](wikipedia)
![]()
次は、
天王星を見ます。
![]()
![]()
![]()



今年の振り返り:
惑星神を見ていると、資料が、フィレンツェでなくもう少し北の、エミリア・ロマーニャ州当たりが中心のようであった。
ラヴェンナ、ボローニャ、モデナには駆け足で2017年に行ったのだがやっぱり、もう少しゆっくり行きたかった。
この1月には、北イタリアにも行こうと思っていた。
ローマからでなく、ヨーロッパの北のアムステルダムからフランスのアルルまで南下して、そのあと東に移動というコースで考えていた・・(ルビコン川は渡らない)
COVID-19 で実施に行くのは無理になったが、10月にようやく、
この3年の旅の写真整理を始めた。来年も、ウェブの旅になるか思うが、冬の課題は旅写真のまとめとします。
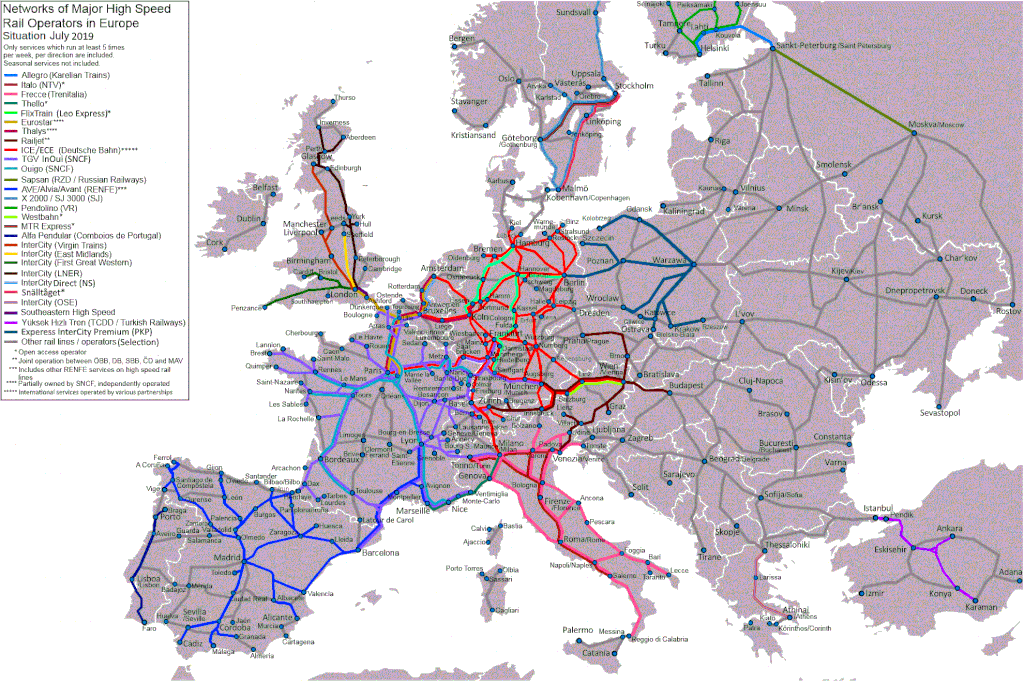
※ルビコン川
ローマ人は、現在の北イタリア一帯に属州ガリア(ガリア・キサルピナ)を置いた。属州と本土との境界は、アドリア海側ではラヴェンナとリミニの中間を流れているルビコン川(現在のルビコーネ川、フォルリ=チェゼーナ県東部)であった。
※ルビコン川を渡る→ご存知の通り(^-^;紀元前49年1月10日、シーザー51歳、ちなみに私の英雄はブルータスの方。

photo 20170607

モデナ大聖堂のクリプト

モデナ大聖堂のポータルのレリーフ

ギャラリアエステンセ@モデナの
アイオン/パネス
(photo byM 20170607)
Rilievo con Aion/Phanes entro lo Zodiaco
(アイオンの救済/獣帯の中のパネス)