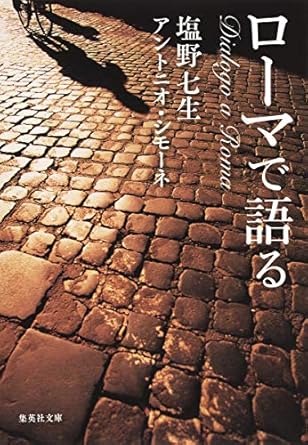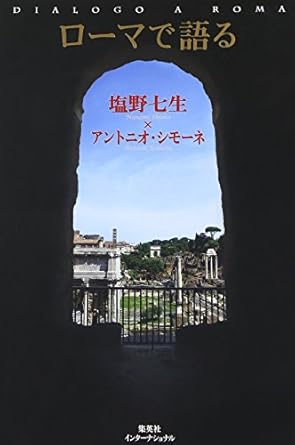
2006年6月から2009年1月の雑誌での
塩野七生さんと息子さんの対談をまとめた本であるが、
書物と映画は同格という家で育てられたと書いておられるのでびっくり・・
息子にも同じ教育を与えたのて、
対話のテーマとして、映画は最適であったが、
息子とは映画の好みが少し違うというのも、もっとも、、、
相当に重なっていても違いがあるということで、例として、
日本製のゴジラとハリウッド製のゴジラの違いは、アメリカ製のは逃げまわるのに、日本製のゴジラは絶対に逃げない。
日本製のゴジラが世界的に成功した原因はそこにあるといわれても、
「ゴジラ」も、「スター・ウォーズ」も見に行かなかったと前書きで塩野さん曰く・・
また、巻末の方で、芸術映画好きの塩野さんと違って、いわゆるアクション・ムービーにも偏見なく接してきたボク、という息子さん。
塩野七生、最初で最後の親子対談集
映画をきっかけにイタリアに移り住んだ塩野七生と、黒澤明と会ったことをきっかけに映画の道に進んだ長男アントニオによる映画対談集。日本、イタリア、アメリカの文化の違いが浮き彫りになる。
その1のタイトルは、「これだけは観てほしいイタリア映画」であるが、
戦火のかなた(1946)
自転車泥棒(1948)
山猫(1963)
フェリーニのローマ(1972)p、
・・で渋い!?です・・
「イタリアン・ネオリアリズム」の作品という
一番目は見ていない。
「戦火のかなた」原題は「パイザ」でナポリ方言で、名もなき地元の庶民という意味だと、息子さん。

Paisà (1946)
アマゾンプライムの見放題になっています・・
後程気合を入れて、みたい。(気合が必要(;^_^A)

Una inquadratura di “Ladri di biciclette” con Enzo Staiola e Lamberto Maggiorani (De Sica, 1948)
こういう企画が続いているのですね・・
英語版wikipediaは年代順に充実
仏蘭西版は人物紹介が多い
中國はそっけないですね
ドイツ版では、イタリア映画の市場シェア情報とともに
1970年代後半から1980年代半ばにかけて、イタリア映画界は長い危機の時代を経験したが、
1990年代のイタリア映画のルネサンスの礎となったのは『シネマ・パラダイス』であり、この作品でジュゼッペ・トルナトーレは1990 年にアカデミー外国語映画賞を受賞した
・・とあり。
イタリア本国wikipediaはこんな
70 年代の終わりから、危機の最初の兆候が感じられ、それは80 年代半ばに爆発し、浮き沈みをしながら今日まで続いています。この産業危機がどれほどの規模であったかを知るには、1985年に映画製作本数がわずか80本(戦後最低)であり、観客動員数が1970年の5億2500万人から1億2300万人に減少したことを考えれば十分だろう。
「パーフェクト・ストレンジャーズ(2016年)」も言及する価値がある。コメディとドラマの見事な組み合わせで、批評家と観客の両方から高い評価を受け、ニューヨークのトライベッカ映画祭で脚本賞などを獲得し、その後、国際的に何度もリメイクされ、25回に達し、2019年7月15日には、世界の映画史上最もリメイクされた映画として ギネスブックに登録された。 2016年から2017年、2017年から2018年、2018年から2019年のシーズンでは観客数が再び減少し、イタリア作品は年間で最も視聴された映画のトップ10に入ることができませんでした
映画を見ていないですね。魅力がなくなった・・・・
アメリカ映画の方、アメリカ合衆国の映画 – Wikipedia
1910年代から1930年代末ごろにかけてが「ハリウッド黄金期」だったと近年では考えられている
2010年代以降、大物俳優のギャラが低下し、CGや大規模なアクションシーンの撮影にお金を費やす傾向が強い。収益の見込めるスタッフによる大作、過去作のリメイクや続編、リブート、他国の映画のリメイクに加え、比較的経費が少ないドキュメンタリー映画などに頼らざるを得ないのが現状である
今・・映画を見ていない・・